第29回 管理栄養士の過去問と解答を全問題表示しています。
- 子宮がん検診 --- 一次予防
- 粉じん作業における保護具の着用 --- 一次予防
- 野外活動前の虫除け剤の使用 --- 二次予防
- 腎不全患者に対する人工透析 --- 二次予防
- BCG の接種 --- 三次予防
【 解答:2 】
- バーゼル条約
- ラムサール条約
- 京都議定書
- カルタヘナ議定書
- モントリオール議定書
【 解答:5 】
- 救急搬送者数は、最近10 年間横ばいである。
- 患者の半数以上は、九州・沖縄地方で発生する。
- 屋内での発症は、ほとんど見られない。
- 予防のための指標として、湿球黒球温度(WBGT)がある。
- 熱痙攣の発症直後には、電解質を含まない水を与える。
【 解答:4 】
- 総人口は、約1 億1 千万人である。
- 自然増減数は、マイナスである。
- 合計特殊出生率は、減少している。
- 従属人口指数は、減少している。
- 人口構造は、ピラミッド型を示している。
【 解答:2 】
- マイナスの値はとらない。
- コホート研究によって得られる。
- ハザード比が含まれる。
- 曝露の除去により予防可能な人口割合を示す。
- 曝露群と非曝露群におけるリスクの比として求められる。
【 解答:4 】
- 習慣的なビタミンC 摂取量と脳血管疾患発症との関連 --- 横断研究
- 国別の喫煙率と肺がん死亡率との関連 --- 生態学的研究
- ある年の健診で把握されたBMI と収縮期血圧との関連 --- コホート研究
- 石綿(アスベスト)への職業性曝露と悪性中皮腫発症との関連 --- 症例対照研究
- 妊婦における食品からの有機水銀摂取量と胎児影響との関連 --- 介入研究
【 解答:24 】
- 介入研究では、介入群・対照群の割付を行う。
- エビデンスの質は、コホート研究より横断研究の方が高い。
- 関連文献を収集する際は、偏りを小さくする。
- メタアナリシスでは、複数の研究データを数量的に合成する。
- 保健対策の優先順位を決める際には、疾病負担の大きさを考慮する。
【 解答:2 】
- 糖尿病腎症による年間新規透析患者数の減少
- 介護保険サービス利用者の増加の抑制
- COPD(慢性閉塞性肺疾患)の死亡率の減少
- 住民が運動しやすいまちづくり・環境整備に取り組む自治体数の増加
- 健康格差対策に取り組む自治体の増加
【 解答:3 】
- 18 歳未満に関しては、基準値は示されていない。
- 年齢を問わず、強度が3 メッツ以上の身体活動が推奨されている。
- 保健指導の一環として行う運動指導の考え方が示されている。
- 身体活動は、社会参加の場として重要である。
- 身体活動は、メンタルヘルス不調の一次予防として有効である。
【 解答:2 】
- 受動喫煙防止対策として、健康増進法に施設管理者に対する罰則規定が定められている。
- たばこ煙中のタールは、依存症の原因となる。
- 医療機関で保険による禁煙治療を受けるのに、喫煙の本数や年数は関係ない。
- たばこ規制に関する世界保健機関枠組条約には、健康警告表示の強化が含まれている。
- 禁煙指導の方法として、低ニコチンたばこの活用がある。
【 解答:4 】
- アルコール依存症の治療では、アルコール摂取量を段階的に減らす。
- 飲酒習慣のある女性の割合は、増加傾向にある。
- 長期の飲酒には、血圧を下げる効果がある。
- 自転車の酒酔い運転は、刑事罰の対象とならない。
- プリン体の少ないアルコール飲料でも、血清尿酸値を上昇させる。
【 解答:5 】
- 「成人病」と同義である。
- 健康日本21(第二次)では、NCD(非感染性疾患)対策という枠組みでとらえている。
- 一次予防の開始時期は、学童期以降である。
- 医科診療医療費(一般診療医療費)に占める割合は、5 割を超えている。
- 死因別死亡割合は、約6 割である。
【 解答:25 】
- 低身体活動
- タイプA 行動パターン
- 若年発症の虚血性心疾患の家族歴
- 高トリグリセリド血症
- 耐糖能異常
【 解答:3 】
- 腸管出血性大腸菌感染症
- 結核
- デング熱
- エボラ出血熱
- 風疹
【 解答:1 】
- 日本国憲法第9 条に基づいている。
- 医療は、税方式で運営されている。
- 社会保障給付費は、過去10 年間ほぼ一定である。
- 社会保障給付費の内訳で最も多いのは、年金である。
- 社会保障費用の国民負担率は、ヨーロッパ諸国と比べて高い。
【 解答:4 】
- 病院とは、50 人以上の患者を入院させるための医療施設である。
- 無床診療所とは、医師が一人しかいない医療施設である。
- 医療計画は、国が策定する。
- 医療連携体制は、医療計画に記載する。
- 基準病床数とは、各医療機関が備えるべき病床数である。
【 解答:4 】
- 都道府県型の保健所は、市町村保健センターを監督する。
- 全国に約850 か所設置されている。
- 人口動態統計に関する業務を行う。
- 要介護認定を行う。
- 港湾で輸入食品の監視業務を行う。
【 解答:3 】
- 先天性副腎過形成症
- フェニルケトン尿症
- ガラクトース血症
- 先天性甲状腺機能低下症(クレチン症)
- ホモシスチン尿症
【 解答:4 】
- 保険者は、都道府県である。
- 被保険者は、65 歳以上の者である。
- 要介護認定は、主治医により行われる。
- 要介護認定を受けた者は、介護サービスを自分で選択することができる。
- 要介護認定において「非該当」の者は、介護予防事業の対象外となる。
【 解答:4 】
- 国際的なNGO の一つである。
- 日本は、設立当初からの加盟国である。
- 日本は、西太平洋地域事務局に属している。
- 活動によって世界からポリオが根絶された。
- 主としてワクチンを販売して得た資金で運営されている。
【 解答:3 】
- ミトコンドリアでは、解糖系の反応が進行する。
- 粗面小胞体では、ステロイドホルモンの合成が行われる。
- ゴルジ体では、脂肪酸の分解が行われる。
- リソソームでは、糖新生が行われる。
- iPS 細胞(人工多能性幹細胞)は、神経細胞に分化できる。
【 解答:5 】
- フルクトースは、アルドースである。
- フルクトースは、五炭糖である。
- グルコースは、ケトースである。
- リボースは、RNA の構成糖である。
- イノシトール1,4,5 三リン酸は、糖脂質である。
【 解答:4 】
- RNA は、主にミトコンドリアに存在する。
- tRNA(転移RNA)は、アミノ酸を結合する。
- DNA ポリメラーゼは、RNA を合成する。
- cDNA(相補的DNA)は、RNA ポリメラーゼによって合成される。
- ヌクレオチドは、六炭糖を含む。
【 解答:2 】
- ATP の産生は、グルコースの異化の過程で起こる。
- 脱共役たんぱく質(UCP)は、AMP 産生を抑制する。
- AMP は、高エネルギーリン酸化合物である。
- 電子伝達系の電子受容体は、窒素である。
- グルタチオンは、活性酸素産生を促進する。
【 解答:1 】
- アポ酵素は、触媒作用を示す。
- 酵素のアロステリック部位は、基質を結合する。
- アイソザイムは、ミカエリス定数(Km)が同じ酵素である。
- 酵素の反応速度は、至適pH で最大となる。
- 律速酵素は、代謝経路で最も速い反応に関与する。
【 解答:4 】
- c アミノ酪酸(GABA)は、トリプトファンから生成される。
- アドレナリンは、ヒスチジンから生成される。
- ユビキチンは、必須アミノ酸の合成に関与する。
- プロテアソームは、たんぱく質リン酸化酵素である。
- オートファジー(autophagy)は、絶食によって誘導される。
【 解答:5 】
- 肝臓のグリコーゲンは、血糖値の維持に利用される。
- 糖新生は、筋肉で行われる。
- 脂肪細胞中のトリアシルグリセロールの分解は、インスリンにより促進される。
- 脂肪酸合成は、リボソームで行われる。
- β酸化は、細胞質ゾルで行われる。
【 解答:1 】
- 副交感神経終末の伝達物質は、ノルアドレナリンである。
- インスリン受容体は、細胞膜を7 回貫通する構造をもつ。
- グルカゴン受容体刺激は、肝細胞内でcGMP(サイクリックGMP)を生成する。
- 細胞内カルシウムイオン濃度の低下は、筋細胞を収縮させる。
- ステロイドホルモンは、遺伝子の転写を調節する。
【 解答:5 】
- 過呼吸(過換気) --- アシドーシス
- 原発性アルドステロン症 --- アシドーシス
- 激しい嘔吐 --- アルカローシス
- 腎不全 --- アルカローシス
- コントロール不良の1 型糖尿病 --- アルカローシス
【 解答:3 】
- 急性細菌感染の浸潤細胞は、主にリンパ球である。
- 急性炎症では、血管の透過性は低下する。
- アミロイド変性は、脂肪変性の1 つである。
- アポトーシスは、プログラムされた細胞死である。
- 過形成は、組織を構成する細胞の容積が増大する。
【 解答:4 】
- 基準値とは、健常者の測定値の99% が含まれる範囲である。
- 特異度の高い検査は、スクリーニングに適している。
- 心電図のQRS 波は、心房の興奮を反映している。
- CRP(C 反応性たんぱく質)値の上昇は、炎症を反映している。
- CT(コンピュータ断層撮影)は、磁気を利用している。
【 解答:4 】
- 重症急性膵炎の発症直後
- クローン病の急性増悪期
- 下顎骨腫瘍の術後
- 潰瘍性大腸炎による下血直後
- 敗血症による多臓器不全
【 解答:3 】
- GLP- 1(グルカゴン様ペプチド1 )
- TNF-α(腫瘍壊死因子α)
- アディポネクチン
- レプチン
- PAI-1(プラスミノーゲン活性化抑制因子1 )
【 解答:1 】
- ビタミンA --- 壊血病
- ビタミンD --- 骨軟化症
- ビタミンB1 --- くる病
- 葉酸 --- 再生不良性貧血
- ビタミンC --- 夜盲症
【 解答:2 】
- 高尿酸血症は、ピリミジンヌクレオチドの代謝異常症である。
- ウイルソン病は、銅の代謝異常症である。
- 糖原病Ⅰ型では、高血糖がみられる。
- ホモシスチン尿症では、血中チロシン濃度が増加する。
- メープルシロップ尿症は、芳香族アミノ酸の代謝異常症である。
【 解答:2 】
- セクレチン --- 胃酸分泌の促進
- ガストリン --- 胃酸分泌の抑制
- インクレチン --- インスリン分泌の促進
- コレシストキニン --- 膵酵素分泌の抑制
- グレリン --- 摂食抑制
【 解答:3 】
- 食道は、胃の幽門につながる。
- 胃食道逆流症の原因には、食道裂孔ヘルニアがある。
- 食道アカラシアでは、食道の器質的狭窄がみられる。
- 食道静脈瘤の成因には、胆石症がある。
- わが国の食道がんは、腺がんの頻度が高い。
【 解答:2 】
- リンパ液は、鎖骨下動脈に流入する。
- 洞房結節は、左心房に存在する。
- 門脈を流れる血液は、静脈血である。
- 心拍出量は、右心室よりも左心室の方が多い。
- 末梢の血管が収縮すると、血圧は低下する。
【 解答:3 】
- 右心不全では、肺水腫が起こる。
- 血漿BNP(脳性ナトリウム利尿ペプチド)濃度は、上昇する。
- 交感神経系は、抑制される。
- 血中アルドステロン濃度は、低下する。
- 悪液質を伴う患者の予後は、不良である。
【 解答:25 】
- カルシトニンは、カルシウムの再吸収を促進する。
- アルドステロンは、カリウムの再吸収を促進する。
- 副甲状腺ホルモン(PTH)は、リンの再吸収を抑制する。
- バソプレシンは、水の再吸収を抑制する。
- 活性型ビタミンD は、カルシウムの再吸収を抑制する。
【 解答:3 】
- 発汗減少
- 基礎代謝量低下
- 脈拍数減少
- 血清コレステロール値上昇
- 血清甲状腺刺激ホルモン(TSH)値低下
【 解答:5 】
- 脳神経は、31 対である。
- 神経細胞間の接合部は、ニューロンと呼ばれる。
- 摂食中枢は、視床下部にある。
- 副交感神経が興奮すると、唾液分泌は減少する。
- 神経活動電位の伝導速度は、無髄線維が有髄線維より速い。
【 解答:3 】
- 左肺は、上葉、中葉、下葉からなる。
- 気管支喘息では、拘束性障害を呈する。
- 1 秒率とは、1 秒間に呼出する量の1 回換気量に対する割合をいう。
- COPD(慢性閉塞性肺疾患)では、安静時エネルギー消費量(REE)は減少する。
- アドレナリン(エピネフリン)は、気管支を拡張させる。
【 解答:5 】
- 閉経後には、骨吸収は亢進する。
- 変形性関節症は、骨密度の低下によって起こる。
- 骨粗鬆症は、骨の石灰化障害である。
- 大腿骨頸部(近位部)骨折は、男性での発生率が高い。
- 糖質コルチコイド薬の投与は、骨折リスクを高める。
【 解答:15 】
- 卵胞刺激ホルモン(FSH)は、テストステロンの分泌を刺激する。
- 精子には、22 本の染色体が存在する。
- テストステロンは、前立腺から分泌される。
- 性周期の卵胞期には、エストロゲンの分泌が高まる。
- 性周期の黄体期には、子宮内膜が脱落する。
【 解答:4 】
- 赤血球のヘモグロビンは、銅を含む。
- 末梢血中の赤血球には、1 個の核がある。
- 老朽化した赤血球は、脾臓で破壊される。
- 赤血球の寿命は、末梢血中で約30 日である。
- 赤血球の産生は、トロンボポエチンによって刺激される。
【 解答:3 】
- 新生児メレナは、ビタミンB6 欠乏症である。
- 特発性血小板減少性紫斑病(ITP)は、ビタミンK 欠乏症である。
- 壊血病では、プロトロンビン合成が抑制される。
- 血友病は、内因子の欠乏により生じる。
- 播種性血管内凝固症候群(DIC)では、線溶系が亢進する。
【 解答:5 】
- 好中球は、抗体を産生する。
- マクロファージは、抗原提示を行う。
- 形質細胞は、細胞性免疫を担う。
- 母乳中の抗体による免疫は、能動免疫である。
- 抗体は、血漿のアルブミン分画にある。
【 解答:2 】
- 全身性エリテマトーデス(SLE) --- 蝶形紅斑
- 全身性エリテマトーデス(SLE) --- ループス腎炎
- 関節リウマチ --- 急性糸球体腎炎
- シェーグレン症候群 --- 唾液分泌量の減少
- 強皮症 --- 嚥下障害
【 解答:3 】
- 鳥インフルエンザウイルス
- ヒト免疫不全ウイルス(HIV)
- 結核菌
- バンコマイシン耐性腸球菌
- 重症急性呼吸器症候群(SARS)ウイルス
【 解答:3 】
- キャッサバの主成分は、グルコマンナンである。
- じゃがいもの有害成分は、リナマリンである。
- さといもの粘性物質は、ガラクタンである。
- きくいもの主成分は、キトサンである。
- さつまいもの甘味成分は、ホモゲンチジン酸である。
【 解答:3 】
- 米みその製造では、麦麹が用いられる。
- うす口しょうゆの塩分濃度は、濃口しょうゆに比べて低い。
- 本みりんは、アルコールを含まない。
- 野菜の漬物では、乳酸菌が生育する。
- ワインの製造では、酢酸菌が用いられる。
【 解答:4 】
- 飽和脂肪酸の構成割合が大きくなると、ヨウ素価は大きくなる。
- 天然に存在する不飽和脂肪酸は、主にトランス型である。
- リン脂質のリン酸部分は、疎水性を示す。
- 活性メチレン基の多い脂肪酸は、酸化しにくい。
- 不飽和脂肪酸は、酵素的に酸化される場合がある。
【 解答:5 】
- クロロフィルが褐色になるのは、マグネシウムの離脱による。
- アントシアニンが赤色を呈するのは、アルカリ性の条件下である。
- えびやかにをゆでると赤色になるのは、アスタシンの分解による。
- ミオグロビンが褐色になるのは、ヘム鉄の還元による。
- のりを加熱すると青緑色になるのは、フィコシアニンの分解による。
【 解答:1 】
- にんにく --- 酢酸イソアミル
- しいたけ --- レンチオニン
- グレープフルーツ --- 桂皮酸メチル
- きゅうり --- ジアリルジスルフィド
- バナナ --- トリメチルアミン
【 解答:2 】
- 純水の水分活性は、1 である。
- 水分活性が低いほど、酵素反応は早く進行する。
- 中間水分食品は、生鮮食品に比べて水分活性が高い。
- 結合水は、自由水に比べて凍結しやすい。
- 自由水は、食品成分と水素結合を形成している。
【 解答:1 】
- 食品安全委員会は、食品衛生法により設置された。
- 食品衛生監視員を任命するのは、農林水産大臣である。
- 食品添加物公定書を作成するのは、厚生労働大臣及び内閣総理大臣である。
- 食品衛生推進員は、国が委嘱する。
- 管理栄養士免許は、食品衛生管理者の任用資格である。
【 解答:3 】
- 化学物質による発生件数が最も多い。
- 夏期の発生件数が増加傾向にある。
- サルモネラ属菌による発生件数が増加している。
- ノロウイルスによる発生件数は冬期に多い。
- 家庭における発生件数が最も多い。
【 解答:4 】
- 細菌性食中毒の原因菌として、最も多い。
- 主な症状は発熱である。
- 重篤な場合、溶血性尿毒症症候群(HUS)を引き起こす。
- 真空包装食品が主な原因となる。
- 食後数時間で発症する。
【 解答:3 】
- 飲料水から感染する。
- 集団感染が報告されている。
- 水様性下痢が主症状である。
- オーシストに感染性がある。
- 加熱殺菌は無効である。
【 解答:5 】
- ホルムアルデヒド --- 甲状腺障害
- ビスフェノールA --- 腎臓障害
- カドミウム --- 膵臓障害
- 有機水銀 --- 中枢神経障害
- 有機スズ --- 造血器障害
【 解答:4 】
- 食品添加物は、健康増進法で定義されている。
- 指定添加物は、消費者庁長官が指定する。
- 既存添加物は、天然添加物として使用実績があったものである。
- 天然香料は、指定添加物に含まれる。
- 一般飲食物添加物は、既存添加物に含まれる。
【 解答:3 】
- アスパルテーム --- 着色料
- ジフェニル --- 酸化防止剤
- エリソルビン酸 --- 甘味料
- 亜硝酸ナトリウム --- 発色剤
- 次亜塩素酸ナトリウム --- 殺菌料
【 解答:45 】
- 100 g 当たりの脂質が3 g である食品は、「ノンファット」と表示できる。
- 100 g 当たりの熱量が100 kcal である食品は、「カロリー控えめ」と表示できる。
- 100 ml 当たりの糖質が2.5 g である飲料は、「無糖」と表示できる。
- 100 g 当たりのたんぱく質が20 g である食品は、「高たんぱく質」と表示できる。
- 100 g 当たりの食物繊維が1.5 g である食品は、「食物繊維入り」と表示できる。
【 解答:4 】
- さばを原材料とする食品には、表示が義務づけられている。
- 落花生を原材料とする食品には、表示が奨励されている。
- 特定原材料であっても、表示が免除されることがある。
- 一括表示は認められていない。
- 「アイスクリーム」は、乳の代替表記として認められていない。
【 解答:3 】
- 大豆油製造で抽出に使用されたヘキサン
- 飲料に栄養強化の目的で使用されたL アスコルビン酸
- 表面積がせまい包装袋のスナック菓子に使用された甘味料
- せんべいに使用されたしょうゆに含まれる保存料
- 寒天ゼリーに使用されたフルーツソースに含まれる着色料
【 解答:5 】
- カルシウム、熱量、たんぱく質、脂質、炭水化物、ナトリウム
- ナトリウム、カルシウム、たんぱく質、脂質、炭水化物、熱量
- たんぱく質、ナトリウム、熱量、脂質、炭水化物、カルシウム
- 熱量、たんぱく質、脂質、炭水化物、ナトリウム、カルシウム
- 熱量、脂質、たんぱく質、炭水化物、カルシウム、ナトリウム
【 解答:4 】
- 紅茶の製造 --- α-アミラーゼ
- 異性化糖の製造 --- インベルターゼ
- 低乳糖牛乳の製造 --- マルターゼ
- チーズの製造 --- キモシン
- 柑橘果汁の苦味除去 --- ペクチナーゼ
【 解答:4 】
- 豆腐 --- 大豆を暗所で発芽させる
- アルファ化米 --- 米を炊飯後急速に冷却し、乾燥させる
- ジャム --- 果実に砂糖を加え、加熱濃縮する
- かまぼこ --- 魚肉を塩漬し、くん煙する
- 糸引き納豆 --- 大豆にコウジカビを接種する
【 解答:3 】
- チルドでは、食品の温度を-10℃ 付近に保つ。
- 冷凍では、一般的な微生物の生育は促進される。
- 砂糖漬けでは、浸透圧が低下する。
- 噴霧乾燥では、低温で食品を乾燥させる。
- CA 貯蔵では、二酸化炭素濃度を大気よりも上昇させる。
【 解答:5 】
- 水蒸気が容易に透過する包装容器を使用する。
- 空気が容易に透過する包装容器を使用する。
- 密閉しない包装を行う。
- 包装容器に窒素を充填する。
- 包装容器に酸素を充填する。
【 解答:4 】
- 嗜好性評価のために選ばれた集団を、パネルという。
- 分析型の官能評価では、食べ物の嗜好性を調べる。
- 3 点比較法では、3 種類の試料を用いる。
- 評価尺度法では、試料間に相対的な順位をつける。
- SD(Semantic Differential)法では、特性を自由記述する。
【 解答:1 】
- 完全に凝固する温度は、卵白より卵黄のほうが高い。
- カスタードプディングでは、砂糖を多くすると凝固が抑制される。
- 卵白を泡立てるときは、砂糖をはじめから加えると泡立てやすい。
- 茶わん蒸しでは、すだち防止のため蒸し器内を95℃ に保つとよい。
- マヨネーズは、油中水滴型(W/O 型)のエマルションである。
【 解答:2 】
- 豆に重曹を加えて煮ると、ビタミンB1が分解される。
- 黒豆のアントシアニンは、鉄イオンと錯体を作って色が安定する。
- 大豆は、珠孔から吸水する。
- 小豆のタンニンは、不味成分なので渋切を行う。
- 小豆の赤色系色素は、種皮に含まれる。
【 解答:解答無し 】
- 本膳料理は、江戸時代に始まった食事様式である。
- 精進料理は、植物性食品を中心にした食事様式である。
- 普茶料理は、肉類を用いるのが特徴である。
- 懐石料理は、本来、茶事の後に供される。
- 会席料理は、はじめに飯と汁が出る。
【 解答:2 】
- たんぱく質 --- クワシオルコル(kwashiorkor)
- 脂質 --- 貧血
- ビタミンD --- 頭蓋内圧亢進
- カルシウム --- ミルクアルカリ症候群(カルシウムアルカリ症候群)
- 銅 --- ヘモクロマトーシス(hemochromatosis)
【 解答:4 】
- 摂食行動は、ストレスの影響を受けない。
- 食欲は、迷走神経の影響を受ける。
- 摂食中枢は、動脈中と静脈中のグルコース濃度の差が大きいと、興奮する。
- レプチンの分泌は、体脂肪率が上昇すると減少する。
- 消化酵素の日内リズムは、食事の影響を受ける。
【 解答:25 】
- 生物学的消化とは、食塊を破砕・混合することである。
- 胃液分泌は、迷走神経が亢進すると促進される。
- ガストリン分泌は、胃に食塊が入ると抑制される。
- セクレチン分泌は、胃内容物が小腸に入ると抑制される。
- 胆汁酸分泌は、ガストリンにより促進される。
【 解答:2 】
- 難う蝕性
- 食後の血糖値上昇抑制
- 大腸の蠕動運動抑制
- 腸内細菌叢改善
- 短鎖脂肪酸の生成
【 解答:3 】
- たんぱく質の平均半減期は、肝臓よりも骨格筋の方が短い。
- 食後に血糖値が上昇すると、筋肉たんぱく質の分解は促進される。
- エネルギー摂取量が減少すると、たんぱく質の必要量は減少する。
- 分枝アミノ酸のアミノ基は、骨格筋でアラニン合成に利用されない。
- グルタミンは、小腸粘膜のエネルギー源となる。
【 解答:5 】
- 無たんぱく質食摂取時にも、尿中へ窒素が排泄される。
- 正味たんぱく質利用率は、吸収された窒素量のうち、体内に保留された割合である。
- アミノ酸価は、含有するアミノ酸総量で決められる。
- アミノ酸インバランスとは、制限アミノ酸の補充で栄養価を改善することである。
- 窒素出納は、エネルギー摂取量の影響を受けない。
【 解答:1 】
- 筋肉グリコーゲンは、分解されて血中グルコースになる。
- 脂肪酸は、グルコースの合成材料になる。
- 乳酸は、グルコースの合成材料になる。
- グルカゴンは、血糖値を低下させる。
- インスリンは、血中グルコースの脂肪組織への取り込みを抑制する。
【 解答:3 】
- オレイン酸は、必須脂肪酸である。
- リノール酸は、体内でパルミチン酸から合成される。
- a リノレン酸は、一価不飽和脂肪酸である。
- エイコサペンタエン酸は、エイコサノイドの合成材料である。
- ドコサヘキサエン酸は、n 6 系の脂肪酸である。
【 解答:4 】
- 肝臓において、トリアシルグリセロールの合成が亢進する。
- 肝臓から、カイロミクロン(キロミクロン)が分泌される。
- 肝臓において、ケトン体の生成が亢進する。
- 筋肉において、エネルギー源としての遊離脂肪酸の利用が亢進する。
- 脂肪組織において、遊離脂肪酸の放出が亢進する。
【 解答:1 】
- エネルギー消費量が多いと、ナイアシンの必要量は増加する。
- たんぱく質の摂取量が多いと、ナイアシンの必要量は増加する。
- たんぱく質の異化が亢進すると、ビタミンB6の必要量は増加する。
- 核酸の合成が亢進すると、葉酸の必要量は増加する。
- 日照を受ける機会が少ないと、ビタミンD の必要量は増加する。
【 解答:2 】
- クロムは、多量ミネラルである。
- 副甲状腺ホルモン(PTH)は、骨へのカルシウムの蓄積を促進する。
- 血中カルシウムイオン濃度の低下は、骨吸収を促進する。
- 体内のリンの80% 以上は、細胞内液に存在する。
- マグネシウムを大量に摂取すると、便秘が誘発される。
【 解答:3 】
- 鉄は、ビタミンB12 の構成成分である。
- 亜鉛の過剰摂取によって、味覚障害が起こる。
- 銅は、セルロプラスミンの構成成分である。
- ヨウ素は、70% 以上が肝臓に存在する。
- セレンは、スーパーオキシドジスムターゼ(SOD)の構成成分である。
【 解答:3 】
- 栄養素の代謝で産生する水は、不感蒸泄で喪失する水より多い。
- 糞便中に排泄される水分量は、尿量より多い。
- 不可避尿量は、水分摂取量の影響を受けない。
- 消化管に流入する水の約50% が吸収される。
- ナトリウムイオン濃度は、組織間液に比べて細胞内液で高い。
【 解答:3 】
- 基礎代謝量は、食後1 時間以内に測定する。
- 基礎代謝基準値(kcal/kg 体重/日)は、年齢とともに増加する。
- 基礎代謝量は、同じ体重で比べると、体脂肪率の高い方が低い。
- 安静時代謝量は、睡眠時代謝量より低い。
- 食事誘発性熱産生は、同じ重量で比べると、たんぱく質より脂肪の方が大きい。
【 解答:3 】
- スクリーニング --- リスクによるふるい分け
- アセスメント --- 目標の設定
- 計画 --- 栄養状態の判定
- モニタリング --- 事業改善の提言
- フィードバック --- 中間の評価
【 解答:1 】
- 推定平均必要量(EAR)
- 推奨量(RDA)
- 目安量(AI)
- 耐容上限量(UL)
- 目標量(DG)
【 解答:1 】
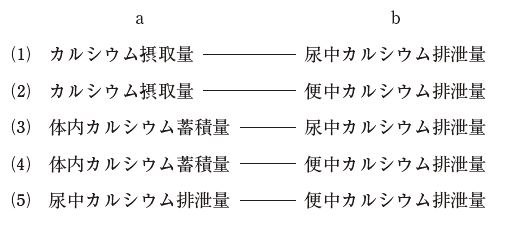
【 解答:3 】
- 低出生体重児とは、出生体重が3,000 g 未満の児をいう。
- リンパ組織の機能的成長は、学童期で最低となる。
- 1 年間の体内カルシウム蓄積量は、成人期に最大となる。
- 塩味閾値は、高齢者で上昇する。
- 唾液分泌量は、高齢者で増加する。
【 解答:4 】
- 細胞内液量は、増加する。
- 収縮期血圧は、上昇する。
- 糸球体濾過量は、増加する。
- 肺活量は、増加する。
- 細胞内テロメアは、長くなる。
【 解答:2 】
- 吸啜刺激は、オキシトシンの分泌を低下させる。
- 吸啜刺激は、プロラクチンの分泌を低下させる。
- 分泌型IgA は、成熟乳より初乳に多く含まれる。
- 母乳には、牛乳よりたんぱく質が多く含まれる。
- 母親の摂取したアルコールは、母乳に移行しない。
【 解答:3 】
- たんぱく質
- 葉酸
- カルシウム
- 鉄
- 亜鉛
【 解答:3 】
- 離乳食は、1 日1 回から与える。
- 卵は、卵黄(固ゆで)から全卵へ進めていく。
- 歯ぐきでつぶせる固さのものを与えるのは、生後5 、6 か月頃からである。
- 咀しゃく機能は、生後12 か月頃までに完成する。
- 哺乳反射の減弱は、離乳完了の目安となる。
【 解答:12 】
- 脈拍数は、年齢とともに増加する。
- 体重当たりの体水分量は、成人に比較して少ない。
- 新生児の生理的黄疸は、生後2 、3 日頃に出現する。
- 乳歯は、生後2 、3 か月で生え始める。
- 血清免疫グロブリン(IgG)値は、生後3 か月まで上昇する。
【 解答:3 】
- 思春期前に比べ、皮下脂肪量は減少する。
- 貧血は、巨赤芽球性貧血が多い。
- 年間身長増加量が最大となる時期は、女子が男子より遅い。
- 急激な体重減少は、月経異常の原因となる。
- 神経性食欲不振症では、過食を起こすことはない。
【 解答:4 】
- 体脂肪率は、増加する。
- インスリン抵抗性は、低下する。
- 血清LDL コレステロール値は、上昇する。
- エストロゲンの分泌は、低下する。
- 骨密度は、低下する。
【 解答:2 】
- 身体機能の個人差は、小さくなる。
- 食物の胃内滞留時間は、短縮する。
- 嚥下反射は、低下する。
- 温冷感は、鋭敏になる。
- 口渇感は、鋭敏になる。
【 解答:3 】
- 1 回心拍出量は、減少する。
- 骨密度は、低下する。
- 筋肉のグルコースの取り込みは、増加する。
- 血清トリグリセリド値は、上昇する。
- 血清HDL コレステロール値は、低下する。
【 解答:3 】
- 熱中症予防には、少量ずつこまめに飲水する。
- 栄養補助食品によるミネラルの補給時には、耐容上限量(UL)以上の摂取を目指す。
- 減量時には、除脂肪体重の減少を目指す。
- スポーツ性貧血の管理には、たんぱく質摂取が重要である。
- 筋グリコーゲンの再補充には、脂質摂取が重要である。
【 解答:14 】
- 副腎皮質刺激ホルモン(ACTH)の分泌は、低下する。
- 交感神経の活動は、減弱する。
- エネルギー代謝は、抑制される。
- 遊離脂肪酸の生成は、増加する。
- 尿中窒素排泄量は、減少する。
【 解答:4 】
- 食欲は、増加する。
- 尿中カルシウム排泄量は、増加する。
- 筋肉量は、増加する。
- 循環血液量は、増加する。
- 血液の分布は、下肢方向にシフトする。
【 解答:2 】
