第29回 管理栄養士の過去問と解答を全問題表示しています。
- 身体活動では、1 日60 分以上の強い運動を勧める。
- 喫煙では、サプリメントを摂取すれば、吸っても良いと伝える。
- 休養では、能動的休養として社会活動への参加を勧める。
- 睡眠では、入眠前のアルコール摂取を勧める。
- 食事では、若い頃よりも味覚が鋭敏になっていることに気づかせる。
【 解答:3 】
- 職場の自動販売機を見て、つい缶コーヒーを買った。
- 同僚のおかわりにつられて、ご飯のおかわりをした。
- 仕事のストレスがたまり、食べ過ぎた。
- 上司のダイエットがきっかけになり、ダイエットを始めた。
- なかなか体重が減らないので、ダイエットをやめた。
【 解答:5 】
- 毎年インフルエンザに罹るが、いつも1 日で回復し寝込むことはない。
- がんによる死亡率は高いが、近親者でがんになった者はいない。
- 糖尿病の合併症の深刻さはわかるが、自分の血糖値は気にならない。
- これまで貧血に罹ったこともないし、貧血で死ぬことはない。
- 両親とも高血圧が原因で脳卒中になったので、自分の血圧が心配である。
【 解答:5 】
- 最初は、肥満改善指導のために開発された。
- 行動変容段階(ステージ)と行動変容過程(プロセス)が含まれる。
- 行動変容段階は、行動変容の準備性によって分けられている。
- 行動変容段階が進むと、自己効力感(セルフ・エフィカシー)も高まる。
- 維持期の対象者でも、関心期(熟考期)に戻ることがある。
【 解答:1 】
- 早朝から、朝食のサービスを提供する。
- 学生が選んだメニューについて、改善点を指摘する。
- 食育フェアを開催し、簡単に調理できるレシピを提供する。
- 食堂の全メニューに、わかりやすい栄養表示を行う。
- 食堂のテーブルに、食生活に関する卓上メモを置く。
【 解答:2 】
- 食事と運動では、どちらを先に改善できそうですか。
- 減量するのは自分のためですか、それとも家族のためですか。
- 1 か月の減量目標は1 kg にしますか、それとも2 kg にしますか。
- 減量はすぐに始めますか、それとも来月からにしますか。
- 減量のメリットとデメリットは、どちらを強く感じますか。
【 解答:5 】
- 空腹でイライラしても3 分間がまんする --- セルフモニタリング
- 食べたくてがまんできなくなったら運動をする --- 認知再構成
- 特別な食事ではなく健康な食事であると考える --- 行動置換
- 食事療法を妨害する人から遠ざかる --- 刺激統制
- 落ち込んだら家族に愚痴を聞いてもらう --- 行動契約
【 解答:4 】
- 食塩を減らす実践に結びつきやすい講演会を開催する。
- 減塩のポイントをまとめたリーフレットを健康フェアで配布する。
- 自治体のホームページでおいしい減塩料理を紹介する。
- スーパーマーケットで食塩相当量を表示した減塩弁当を販売する。
- 減塩の調味料を使用する飲食店を増やす。
【 解答:4 】
- 消費期限は、品質保持が期待できる期限を示した表示です。
- 賞味期限は、その期限内に食べることを定めた表示です。
- ナトリウム1,000 mg の食塩相当量は、1 g になります。
- アレルギー表示の特定原材料として、5 品目が定められています。
- 「熱量ゼロ」と表示されていても、0 kcal とは限りません。
【 解答:5 】
- 社員全員の身長、体重、腹囲を計測する。
- 生活習慣改善に対する考え方を個別面談で調べる。
- 社員食堂の献立別の売り上げを調べる。
- 職場周辺にある飲食店のメニューを調べる。
- 社員全員の栄養摂取状況を調べる。
【 解答:2 】
- 幼稚園児が、正しい箸の持ち方の紙芝居を観る。
- 小学生が、苦手な食べ物を克服するための寸劇をする。
- 中学生が、栄養素の種類と働きについて講義を受ける。
- 高校生が、朝食欠食の問題点と改善策について話し合う。
- 勤労者が、生活習慣病予防対策のビデオを観る。
【 解答:4 】
- 主食 --- 炭水化物100 g
- 副菜 --- 食物繊維7 g
- 主菜 --- たんぱく質6 g
- 牛乳・乳製品 --- カルシウム200 mg
- 果物 --- ビタミンC 100 mg
【 解答:3 】
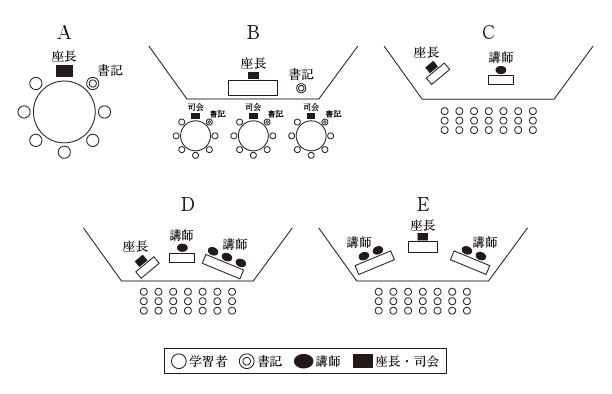
- フォーラム --- A
- シンポジウム --- B
- バズセッション --- C
- ラウンドテーブルディスカッション --- D
- パネルディスカッション --- E
【 解答:5 】
- プログラムに競技指導者との連携が含まれていたか --- 企画評価
- 選手の乳製品の摂取量が増加したか --- 経過(過程)評価
- 選手の1 年後の骨密度が増加したか --- 影響評価
- 選手の食事と競技パフォーマンスに関する知識が増えたか --- 結果評価
- 弁当を手作りすることで、選手の食費が節約できたか --- 経済評価
【 解答:1 】
- 学校医から未成年者の飲酒の害を聞く。
- 酒造メーカーの人と教授との対談を聞く。
- 断酒会の人たちから断酒の苦労を聞く。
- 急性アルコール中毒になった先輩と話をする。
- アルコール依存症の人のビデオを観る。
【 解答:4 】
- コンプライアンス --- 痛みを抑える治療
- アドヒアランス --- 患者側の治療への積極的な参加
- ノーマリゼーション --- 患者の重症度の判別
- セカンドオピニオン --- 患者の意思の確認
- トリアージ --- 別の専門職の意見を求めること
【 解答:2 】
- アウトカムは、開始後に設定する。
- 目的に、治療の標準化がある。
- バリアンスは、パス終了後に対応する。
- 活用により、チーム医療が不要となる。
- インフォームドコンセントが必要である。
【 解答:25 】
- 下腿周囲長 --- 身長
- 肩甲骨下部皮下脂肪厚 --- 上腕筋囲
- 膝下高 --- 上腕筋面積
- ウエスト周囲長 --- 内臓脂肪面積
- 上腕周囲長 --- 体脂肪率
【 解答:4 】
- 末梢血リンパ球数 --- 骨格筋量
- 血清トランスサイレチン値 --- 体脂肪量
- 血清トランスフェリン値 --- 骨量
- 血清レチノール結合たんぱく質値 --- 筋たんぱく質量
- 尿中3-メチルヒスチジン量 --- 筋たんぱく質異化量
【 解答:5 】
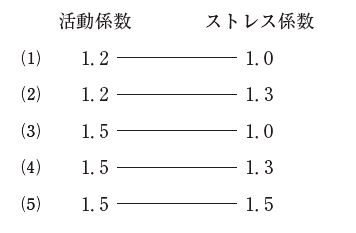
【 解答:2 】
- 入院患者は、1 週間に2 回算定できる。
- 外来患者は、初回月に3 回算定できる。
- 集団栄養食事指導料は、1 回の指導時間30 分で算定できる。
- 集団栄養食事指導料は、入院患者と外来患者を同時に指導しても算定できる。
- 成人の食物アレルギー食は、算定対象である。
【 解答:4 】
- 人工濃厚流動食には、ミキサー食が含まれる。
- 小腸切除例の適応判断基準に、残存腸管の長さは含まれない。
- 開始時の投与速度は、50 mL/時以下とする。
- 下痢が生じた場合は、投与速度を速める。
- 脱水が生じた場合、血清尿素窒素値が低下する。
【 解答:3 】
- 生理食塩液のナトリウム濃度は、154 mEq/L である。
- 高カロリー輸液製剤には、クロムが含まれる。
- 中心静脈栄養法と経腸栄養法は併用できない。
- 脂肪乳剤は、末梢静脈から投与できない。
- ビタミンB1 欠乏では、代謝性アルカローシスを発症する。
【 解答:1 】
- 血清トリグリセリド値の低下がみられる。
- 血清リン値の上昇がみられる。
- 血清カリウム値の上昇がみられる。
- 血清マグネシウム値の低下がみられる。
- 血清インスリン値の低下がみられる。
【 解答:4 】
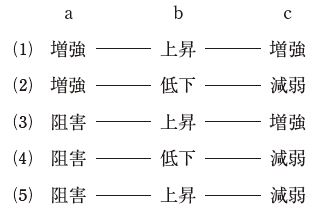
【 解答:3 】
- 内臓脂肪型肥満は、内臓脂肪面積120 cm2 以上をいう。
- 高度肥満は、BMI 30 kg/m2 以上をいう。
- 睡眠時無呼吸症候群は、肥満合併症である。
- 変形性関節症には、脂肪細胞の量的異常が関与する。
- 超低エネルギー食(VLCD)は、1,000 kcal/日とする。
【 解答:34 】
- 炭水化物の摂取エネルギー比率は、70% とする。
- たんぱく質の摂取エネルギー比率は、7 % とする。
- コレステロールの摂取量は、400 mg/日とする。
- 食塩の摂取量は、10 g/日とする。
- 食物繊維の摂取量は、25 g/日とする。
【 解答:5 】
- エネルギーの摂取量は、1,200 kcal/日とする。
- 飽和脂肪酸の摂取量は、13 g/日とする。
- コレステロールの摂取量は、400 mg/日とする。
- 食塩の摂取量は、8 g/日とする。
- アルコールの摂取量は、エタノール換算で40 g/日とする。
【 解答:2 】
- 原因には、腹圧の上昇がある。
- アルコール摂取により、下部食道括約筋圧が低下する。
- 高脂肪食は、胃排泄速度を遅延させる。
- 1 回の食事量を少なくする。
- 食後は、仰臥位安静とする。
【 解答:5 】
- 潰瘍性大腸炎では、水溶性食物繊維を制限する。
- クローン病では、アミノ酸を制限する。
- 短腸症候群では、糖質を制限する。
- イレウスでは、輸液量を制限する。
- たんぱく質漏出性胃腸症では、脂質を制限する。
【 解答:5 】
- 呼吸商(RQ)低下時は、糖質を制限する。
- フィッシャー比低下時は、芳香族アミノ酸を投与する。
- 高アンモニア血症では、糖質を制限する。
- 腹水時には、脂質を制限する。
- 便秘予防には、ラクツロースを投与する。
【 解答:5 】
- 循環血液量が減少する。
- 心拍出量が増加する。
- 末梢血管抵抗が増加する。
- 交感神経が活性化する。
- 血液浸透圧が高まる。
【 解答:1 】
- エネルギー摂取を増加させる。
- たんぱく質を制限する。
- ビタミンB1 を制限する。
- ナトリウムを制限する。
- カリウムを制限する。
【 解答:4 】
- 病期第1 期では、リンの摂取量を500 mg/日とする。
- 病期第2 期では、エネルギーの摂取量を35 kcal/kg 標準体重/日とする。
- 病期第3 期で高カリウム血症があれば、カリウムの摂取量を4.0 g/日とする。
- 病期第4 期では、たんぱく質の摂取量を0.7 g/kg 標準体重/日とする。
- 病期第5 期(血液透析)では、水分の摂取量を35 mL/kg ドライウェイト/日とする。
【 解答:4 】
- 重症度の分類に、尿中尿素窒素値を用いる。
- たんぱく質摂取量の推定式には、血清尿素窒素値を用いる。
- 食塩摂取量の推定には、血清ナトリウム値を用いる。
- 補正カルシウム濃度は、血清アルブミン値4.0 g/dL 未満で用いる。
- 代謝性アシドーシスの評価には、尿中たんぱく質排泄量を用いる。
【 解答:4 】
- たんぱく質を制限する。
- 水分を制限する。
- 食物繊維を制限する。
- 嚥下能力を確認する。
- ワルファリン使用時は、ビタミンE を制限する。
【 解答:4 】
- エネルギーの摂取量は、2,400 kcal とする。
- たんぱく質の摂取量は、40 g とする。
- 経腸栄養剤は、分枝アミノ酸含量が多いものを選択する。
- 炭水化物の摂取エネルギー比率は、70% とする。
- 脂肪の摂取エネルギー比率は、15% とする。
【 解答:3 】
- 血清ビタミンB12 値の低下
- 平均赤血球容積(MCV)値の上昇
- 白血球数の上昇
- 血小板数の低下
- 血清間接ビリルビン値の上昇
【 解答:3 】
- 歩行速度の測定は、スクリーニングに用いられる。
- 加齢は、要因となる。
- たんぱく質摂取不足は、要因となる。
- 筋力低下は、認めない。
- ADL(日常生活動作)は、低下する。
【 解答:4 】
- 緩和ケアは、がん診断初期から始まる。
- 食道癌根治術後患者では、誤嚥の危険性が高まる。
- 大腸癌術後のストマ(人工肛門)は、空腸に造設する。
- 血清α-フェトプロテイン(AFP)は、肝細胞癌の腫瘍マーカーとなる。
- がん悪液質では、除脂肪量が減少する。
【 解答:3 】
- 食道癌術後は、少量頻回食を適用しない。
- 胃切除後は、鉄の吸収障害を起こす。
- 胆のう摘出後は、胆汁の濃縮機能が亢進する。
- 肝臓切除後は、分枝アミノ酸を制限する。
- 結腸切除後は、水分を制限する。
【 解答:2 】
- チアミン
- リボフラビン
- ナイアシン
- ピリドキシン
- アスコルビン酸
【 解答:4 】
- 妊娠の可能性がある時期では、葉酸のサプリメントは使用しない。
- 妊娠糖尿病の発症率は、肥満者では低くなる。
- 糖尿病合併妊娠例の治療には、インスリン療法は禁忌である。
- 1 日尿量500 mL の妊娠高血圧症候群患者の水分摂取は、前日尿量を考慮する。
- 妊娠性貧血では、ビタミンA を補給する。
【 解答:4 】
- たんぱく質の摂取量は、推定平均必要量とする。
- BMI は、25 kg/m2 以上を目標とする。
- 水分を制限する。
- 血清アルブミン値をモニタリングする。
- ウエスト周囲長をモニタリングする。
【 解答:4 】
- 健常者では、起こらない。
- 睡眠中では、起こらない。
- 不顕性誤嚥では、むせはみられない。
- 経鼻胃管留置では、起こらない。
- 咽頭残留食物の食道への移行は、飲水により行う。
【 解答:3 】
- 科学的根拠に基づいた地域保健活動を推進する。
- 疾病の重症化予防の推進を含む。
- ソーシャルキャピタルを活用する。
- 健康危機管理体制を構築する。
- ポピュレーションアプローチは、高いリスクをもつ個人を対象にする。
【 解答:5 】
- 食物繊維の摂取量は、50 歳以上より49 歳以下で多い。
- 鉄の摂取量は、50 歳以上より49 歳以下で多い。
- 脂肪エネルギー比率が30% 以上の者の割合は、男性より女性で高い。
- 果実類の摂取量は、女性より男性で多い。
- 乳類の摂取量は、女性より男性で多い。
【 解答:3 】
- FOOD ACTION NIPPON とは、食品の安全性の確保に関する国民運動のことである。
- 食品ロス率とは、食品使用量のうち直接廃棄・過剰除去・食べ残し重量の割合をいう。
- フードバランスシート(食料需給表)とは、国内で生産された食料の輸送状況を示したものである。
- フードデザート(food deserts)とは、食品の生産・加工・流通の過程を追跡するシステムのことをいう。
- フードマイレージとは、食料品の購入時の、自宅から店舗までの距離をいう。
【 解答:2 】
- 家計調査によって把握される。
- 国内消費仕向量に対する国内消費量の割合である。
- 品目別食料自給率は、重量ベースで示される。
- 総合食料自給率(供給熱量ベース)は、60% 前後で推移している。
- 総合食料自給率(供給熱量ベース)は、先進国の中で最高水準にある。
【 解答:3 】
- 養成制度の創設は、栄養士より管理栄養士が先である。
- 栄養士名簿は、厚生労働省に備えられる。
- 栄養士法には、特定給食施設に管理栄養士を置くことが定められている。
- 都道府県知事が任命する栄養指導員は、医師又は管理栄養士の資格を有する。
- 特定保健指導に関する専門的知識及び技術を有する者として、栄養士が定められている。
【 解答:4 】
- 健康増進法に基づいて実施する。
- 調査地区の抽出には、層化無作為抽出法を用いる。
- 身体状況調査として、血圧を測定する。
- 栄養摂取状況調査は、連続した3 日間で実施されている。
- 調査は、毎年同時期に実施されている。
【 解答:4 】
- 食生活指針(2000 年)を受けて策定された。
- 人間と食物と環境の関係を示した。
- 食品の無駄な廃棄を削減するために策定された。
- 生活習慣病予防のために必要な身体活動量を示した。
- 食品についての栄養表示の基準を示した。
【 解答:1 】
- 食育基本法に基づいて策定される。
- 食育推進会議において策定される。
- 「食育月間」が定められている。
- 食品の安全性の確保における食育の役割が規定されている。
- 現在の計画の実施期間は、10 年間である。
【 解答:5 】
- 政府開発援助(ODA)によって、栄養士業務の国際基準が検討されている。
- 国際協力機構(JICA)は、海外への栄養士派遣プログラムを運営している。
- 国連開発計画(UNDP)は、「食物ベースの食生活指針」を策定した。
- 国連世界食糧計画(WFP)は、食品の健康表示に関する国際的規格の検討を行っている。
- 世界保健機関(WHO)は、フードバランスシート(食料需給表)の作成方法の基準を定めている。
【 解答:2 】
- 24 時間食事思い出し法は、調査者の技術の影響を受けにくい。
- 秤量による食事記録法は、対象者の負担が少ない。
- 目安量による食事記録法は、食品成分表に記載されていない栄養素の摂取量が把握できる。
- 体重の変化量は、エネルギー収支バランスの指標となる。
- 早朝尿のナトリウム量は、過去数か月間の平均食塩摂取量の指標となる。
【 解答:4 】
- 食事記録法(秤量法)
- 食事記録法(目安量法)
- 24 時間食事思い出し法
- 食物摂取頻度調査法
- 陰膳法
【 解答:4 】
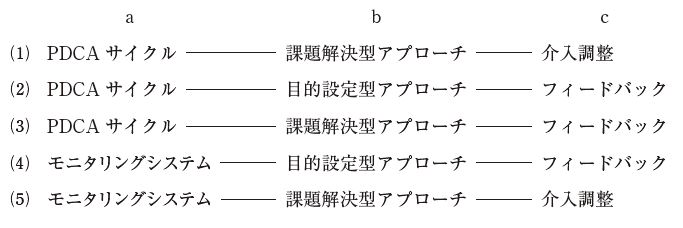
【 解答:3 】
- エネルギーの過剰摂取を防ぐために、エネルギー摂取量の平均値を推定エネルギー必要量(EER)未満にする。
- エネルギー摂取の過不足を防ぐために、BMI の平均値を正常範囲内にとどめる。
- 栄養素の摂取不足を防ぐために、集団の平均摂取量を推定平均必要量(EAR)付近まで改善させる。
- 栄養素の過剰摂取を防ぐために、集団全員の摂取量を耐容上限量(UL)未満にする。
- 生活習慣病の一次予防のために、集団の平均摂取量を目標量(DG)の範囲内にする。
【 解答:4 】
- 選択バイアスを小さくするために、調査対象者は無作為に抽出する。
- 標本調査は、母集団に属する全員を対象者として実施する。
- 文献調査は、調査票によって回答を得る方法である。
- 電話調査法では、自記式質問紙法よりも調査者による情報バイアスがかかりにくい。
- 面接法では、自記式質問紙法よりも対象者に質問の意味が誤解されやすい。
【 解答:1 】
- 限られた予算で全体の傾向を調べるため、無作為抽出調査を行う。
- 同じ時期に多くの対象者を調査するため、郵送法によって行う。
- 自記式質問紙による調査の回収率を上げるため、無記名で実施する。
- 住民の自由な発想に基づく意見を聞くため、グループインタビュー法を用いる。
- 面接法調査における対象者のプライバシー保護のため、調査員の選出を地元の町内会に依頼する。
【 解答:5 】
- 市民の主観的健康度の向上
- 糖尿病有病率の低下
- メタボリックシンドローム該当者数の減少
- 生活習慣病に関連する医療費の減少
- 自身の適正体重を認識する者の割合の増加
【 解答:5 】
- アセスメント実施過程に対する評価が含まれる。
- 経過(過程)評価は、最終目標を評価する。
- 影響評価は、プログラムの実施状況を評価する。
- 結果評価は、行動に影響を与える要因を評価する。
- 評価結果は、公表しない。
【 解答:1 】
- プログラム推進委員会に住民代表の参加を求める。
- 対象住民への問診は、住民代表が実施する。
- プログラムの優先順位決定には、住民の意見を取り入れる。
- 食生活改善推進員によるボランティア活動と連携する。
- プログラムの効果判定時に住民が意見を述べる。
【 解答:2 】
- 地域防災計画へ栄養・食生活支援の具体的内容を位置づける。
- 災害時の栄養・食生活支援マニュアルを作成する。
- 被災地への管理栄養士派遣の仕組みを整備する。
- 家庭における食料備蓄推進の普及啓発活動を行う。
- 管内の給食施設に対し、食料の備蓄は1 日分を推奨する。
【 解答:5 】
- 妊産婦に対する栄養の摂取に関する援助
- 難病患者の食事支援ネットワークの構築
- 特定保健指導
- 独居高齢者に対する配食
- 特定保健用食品の許可
【 解答:2 】
- 栄養士を置かない施設は、行政指導の対象から除外する。
- 栄養管理に必要な指導は、食品衛生監視員が行う。
- 栄養管理上の課題が見られる施設に対して、効果的な指導計画を作成する。
- 指導後には、栄養管理に関する報告書を施設に発行する。
- 栄養管理の基準に違反した場合には、厚生労働大臣が勧告を行う。
【 解答:3 】
- 事業所 --- 労働安全衛生法
- 小学校 --- 学校給食法
- 児童養護施設 --- 児童福祉法
- 養護老人ホーム --- 介護保険法
- 介護老人保健施設 --- 医療法
【 解答:4 】
- 入院基本料は、栄養士の配置が要件である。
- 入院診療計画書には、特別な栄養管理の必要性の有無を記載する。
- 入院時食事療養(Ⅰ)では、「食事は医療の一環として提供されるべきものである」とされている。
- 入院時食事療養(Ⅰ)の特別食加算は、患者の自己負担による。
- 栄養サポートチーム加算は、月1 回の回診が要件である。
【 解答:23 】
- 健康診断の回数は、2 年に1 回とする。
- 炊事従事者の休憩室は、警備員のものと兼ねる。
- 食堂の床面積は、食事の際の1 人について、0.5 m2 以上とする。
- 食堂と炊事場は、作業場内に設置する。
- 1 回100 食以上の給食を行う時は、栄養士を置くように努める。
【 解答:5 】
- 栄養・食事管理 --- 調理室の温度記録
- 食材管理 --- 利用者の栄養アセスメント
- 生産管理 --- 配膳時刻調査
- 衛生管理 --- 食材日計表
- 会計管理 --- 利用者の嗜好調査
【 解答:3 】
- 小学校給食の年間献立計画 --- 教諭
- 介護老人福祉施設の誕生会での食事提供 --- 看護師
- 入院時食事療養(Ⅰ)届出の病院の検食 --- 薬剤師
- 通所介護施設の低栄養状態改善のための栄養食事相談 --- 介護福祉士
- 事業所給食の給与栄養目標量の設定 --- 産業医
【 解答:3 】
- 事業開始時の届出事項である。
- 保育所では、管理栄養士が作成しなければならない。
- 病院の治療食では、該当しない。
- 病院の一般食では、調理業務の受託会社が作成する。
- 事業所給食の経営合理化に活用できる。
【 解答:5 】
- 摂取する食品と健康の保持増進との関連性
- 自然環境の恵沢に対する理解
- 食にかかわる産業の理解
- 地域産物の給食への活用
- 当該学校の教諭に対する栄養管理
【 解答:5 】
- 品質管理の目的は、献立の標準化である。
- 品質管理の活動は、PDCA サイクルにそって行う。
- 設計品質は、調理機器のレイアウトによって示される。
- 適合(製造)品質は、予定献立の食品重量によって示される。
- 総合品質は、利用者の満足度によって示される。
【 解答:25 】
- 総原価とは、食事の生産にかかる費用を金額で表したものである。
- 総原価は、経費と利益で構成される。
- 直接製造費は、材料費と労務費で構成される。
- 直接経費には、調理従事者の健康管理費が含まれる。
- 販売価格は、総原価に販売経費を加えた金額である。
【 解答:4 】
- 野菜類 --- 納入業者に下処理室へ搬入させる。
- 果物類 --- 検収後、納入時の容器で冷蔵する。
- 生鮮魚介類 --- 納入時の品温が10℃ であることを確認する。
- 冷凍食品 --- 納入時の品温が-10℃ であることを確認する。
- 調味料 --- 適正在庫量の範囲内で納入させる。
【 解答:5 】
- 野菜の鮮度 --- 料理の種類数
- 下処理の作業時間 --- 食材の廃棄率
- 作業動線 --- 残食量
- 料理の品質 --- 苦情件数
- 食器の洗浄状態 --- 食器洗浄室の温度
【 解答:4 】
- 配食作業のマニュアル作成
- 空中落下菌検査の採取場所の見直し
- 異なる作業区域間移動のワゴン利用
- 施設・設備機器の定期点検項目の見直し
- 防火対策チェックリスト項目の確認
【 解答:3 】
- 購入後の食品の泥は、除去する。
- 採取する食品の重量は、5 g 前後とする。
- 調理済み食品は、盛り付け前に採取する。
- 保存温度は、-18℃ に設定する。
- 保存期間は、2 週間以上とする。
【 解答:5 】
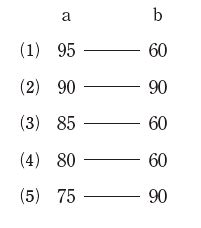
【 解答:2 】
- 災害発生時の人員配置のために、アクシデントレポートを分析する。
- 調理従事者の意識向上のために、インシデントレポートを実施する。
- 異物混入事故を防止するために、検便検査を実施する。
- 調理従事者の転倒防止のために、グリストラップを清掃する。
- 災害時の備蓄食品は、平常時の在庫上限量を維持する。
【 解答:2 】
- 原材料の保管場 --- 清潔作業区域
- 調理済み食品の保管場 --- 汚染作業区域
- 検収場 --- 汚染作業区域
- 調理場 --- 清潔作業区域
- 放冷・調製場 --- 準清潔作業区域
【 解答:3 】
- 作業工程を配慮して、機器・設備を配置する。
- 作業スペースと通路を確保する。
- 作業動線は、双方向・反復を基本とする。
- 食器の動線は、短くする。
- 可動設備を有効利用する。
【 解答:3 】
- 成果は指導者の能力に影響されない。
- 継続的な教育が可能である。
- 個人に対応した目標は設定できない。
- 日常の業務を休まなければならない。
- 内容が日常業務に結びつかない。
【 解答:2 】
- 仕事に対する勤勉性
- 仕事に対する責任感
- 仕事の質と量
- 基礎的な知識
- 理解力と判断力
【 解答:3 】
- 特定健康診査受診者
- 特定保健指導の積極的支援対象者
- 健康教室参加者
- 肝疾患で通院中の住民
- 住民登録している成人
【 解答:5 】
- アルコール依存症患者の生活状況を把握する。
- 飲酒運転撲滅キャンペーンを実施する。
- 未成年者への飲酒販売の禁止を徹底する。
- 「生活習慣病のリスクを高める飲酒量」について、町の広報で周知する。
- 特定保健指導で、1 日2 合以上の飲酒者に健康教育を行う。
【 解答:4 】
身長170 cm、体重66 kg、ウエスト周囲長82 cm、血圧132/80 mmHg。両側のアキレス腱の肥厚を認める。空腹時の血液検査値は、総コレステロール364 mg/dL、HDL-コレステロール54 mg/dL、トリグリセリド110 mg/dL、血糖102 mg/dL、HbA1c 5.5%。肝、腎、および甲状腺機能は正常。
- 糖尿病型である。
- メタボリックシンドロームである。
- 血清LDL コレステロール値は、200 mg/dL と算出される。
- LDL 受容体の異常が考えられる。
- 本態性高血圧である。
【 解答:4 】
身長170 cm、体重66 kg、ウエスト周囲長82 cm、血圧132/80 mmHg。両側のアキレス腱の肥厚を認める。空腹時の血液検査値は、総コレステロール364 mg/dL、HDL-コレステロール54 mg/dL、トリグリセリド110 mg/dL、血糖102 mg/dL、HbA1c 5.5%。肝、腎、および甲状腺機能は正常。
- たんぱく質の摂取量は、0.6 g/kg 標準体重/日とする。
- 脂肪の摂取エネルギー比率は、15% とする。
- 飽和脂肪酸の摂取エネルギー比率は、7 % 以上とする。
- コレステロールの摂取量は、200 mg/日未満とする。
- アルコールの摂取量は、エタノール換算で40 g/日とする。
【 解答:4 】
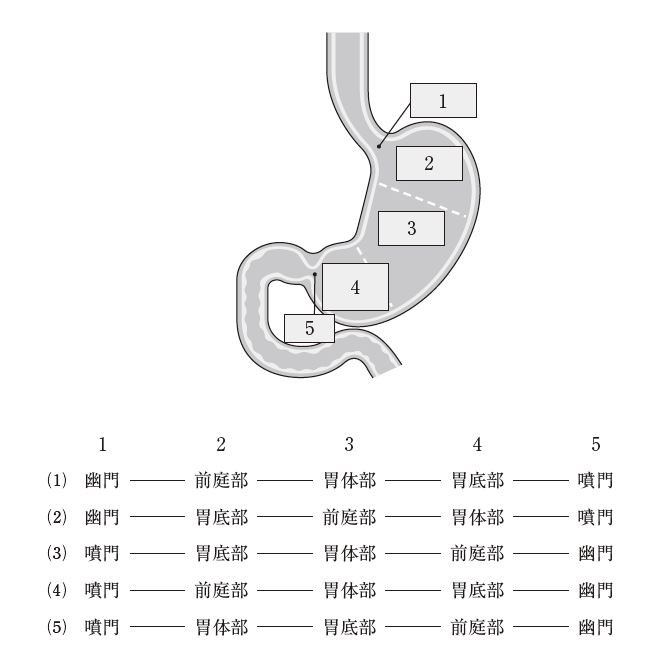
【 解答:3 】
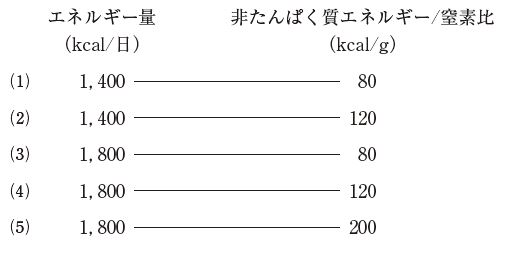
【 解答:4 】
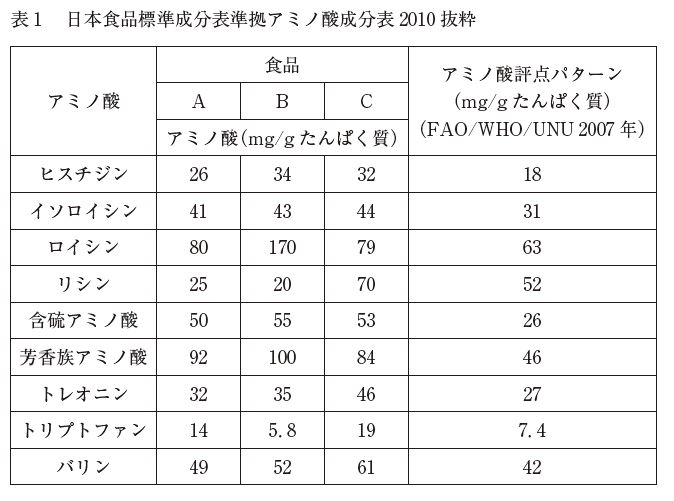
- A のアミノ酸価は、C のアミノ酸価より高い。
- A は、リシンを添加しても栄養価は変わらない。
- B は、トリプトファンが第1 制限アミノ酸である。
- 体内において食品たんぱく質1 g 当たりに生成するナイアシン量(mg)は、B よりC の方が少ない。
- 体内において食品たんぱく質1 g 当たりに生成するナイアシン量(mg)は、A よりB の方が少ない。
【 解答:5 】
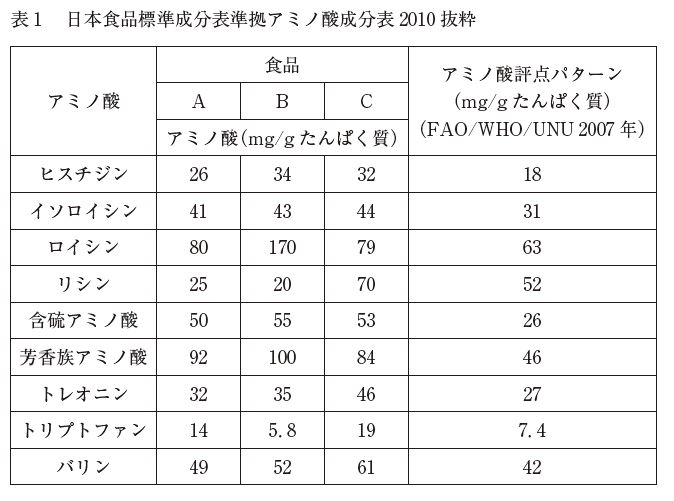
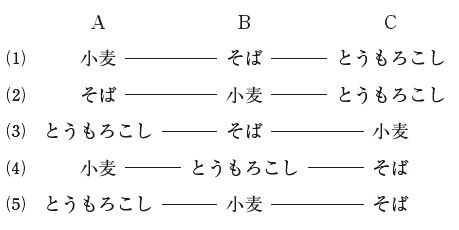
【 解答:4 】
- 血清鉄の高値
- 不飽和鉄結合能(UIBC)の低値
- 血清フェリチンの高値
- 平均赤血球容積(MCV)の高値
- 平均赤血球ヘモグロビン濃度(MCHC)の低値
【 解答:5 】
- 適正なエネルギー摂取には、主食が必要であることが分かる --- 学習目標
- 妊娠30 週目の体重を50 kg にする --- 結果目標
- 鉄分の多い食事を摂る --- 結果目標
- 禁酒する --- 行動目標
- 家庭を禁煙にする --- 環境目標
【 解答:3 】
